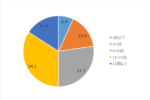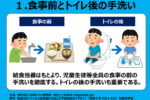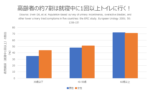これまでに「日本のトイレは困っている」「公共トイレってなんだ?」と題して日本における公共トイレの課題について書いてきました。最後となる今回は「公共トイレの合理的配慮」です。
合理的配慮を知っていますか?
国連は2008年に「障害者の権利に関する条約」を発効しています。日本においては2013年に「障害者差別解消法」を制定、その後2014年に上記条約を批准しています。この障害者の権利に関する条約に「合理的配慮」が出てきます。
「合理的配慮」とは障害のある人が他の人同様の人権と基本的自由を享受できるように、物事の本質を変えてしまったり、多大な負担を強いたりしない限りにおいて、配慮や調整を行うことである。
(障害者権利条約 第2条から抜粋)
合理的配慮をトイレで考えてみたいと思います。たとえば車いすを利用している人がどこかのお店に行こうと思ったところ、そこには車いす対応のトイレがありませんでした。トイレをリフォームできれば一番よいのですが、リフォームする費用やスペースもない。なんてことはいっぱいあります。そこで、合理的配慮ではリフォーム以外の方法でも、利用者の同意があればよいとされています。
具体的には、同意があれば、段差などの障壁は介助によりクリアするなどの配慮をもって課題を解決する(=権利の執行をする)ことができるという意味です。

この合理的配慮について、国の行政機関・地方公共団体・独立行政法人・特殊法人等の場合は、法的義務があります(障害者差別解消法 第七条第2項)。
一方で、民間事業者の場合は、努力義務になっています(以下参照)。
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 第4)民間事業者の場合
障害者が合理的配慮を求めた場合、負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。ただし、事業における障害者との関係が分野・業種・場面・状況によって様々であり、求められる配慮の内容・程度も多種多様であることから、合理的配慮の提供については、努力義務とされている
つまり、不特定多数が使用する民間トイレは、法律では合理的配慮が努力義務です。ですが、公共トイレ数の比率は、圧倒的に民間のトイレが多いことを考えると、民間のトイレにも合理的配慮への期待が大きくなります。民間の大規模施設のトイレは、義務として取り組んでもらえたらありがたいです。
一方で、行政としては民間に頼りっぱなしというわけにもいきません。
行政が設置する多機能トイレの数を増やし、質を向上することも求められます。とくに成人でおむつ利用している方がおむつを交換できるベッドの整備、多機能トイレ内で視覚障害者がスムーズに便器までたどり着くための誘導、ボタン操作に迷わないようにするためのデザインなどです。
また、トイレ整備に積極的に取り組む民間を支援する仕組みも必要だと考えます。官民が協力しながら、だれもが安心して使用できるトイレを増やしていくことが必要です。
今の気持ちを表してみよう!
PICK UP合わせて読みたい記事
-
 そのほか
そのほかトイレと排泄事情~妊娠出産を経験して~
妊娠出産による体の変化とトイレ・排泄事情について。妊娠中、出産後の女性にとって、どんなトイレ環境がいいのか、体験談をご紹介します。
2020.09.24
-
 おすすめトイレ
おすすめトイレNO MORE、トイレ難民!さて、トイレ難民ってだれのことでしょうか?
幼児期から高齢者までオムツ替え等の目的で利用できる『ユニバーサルシート』は、多目的トイレに設置されているベッドです。 しかし認知度はまだまだ低く、設置も進んでいないのが現状です。
2021.08.05
-
 おすすめトイレ
おすすめトイレ女子トイレの問題!生理への対処(MHM)を意識して
女性特有のトイレ・ニーズとして生理への対処があります。発展途上国では特に大きな問題ですが、日本の女子トイレ・ニーズにも共通する点があります。
2021.02.04
-
 おすすめトイレ
おすすめトイレ排泄に関わる障害を持つ「オストメイト」と日本初のスマートフォンアプリ
病気や障害はさまざまな種類があり、外見から分かりやすいものもあれば、一目見ただけでは健康な状態と変わりないといったものもあります。人工肛門、人工膀胱もその中の1つと言え、この人工肛門や人工膀胱を造設した方々をオストメイト […]
2022.02.10
-
 おすすめトイレ
おすすめトイレ車いすユーザー近藤さんとトイレ見学してわかったこと
日本トイレ研究所では皆さまの「お気に入りトイレ」を募集してきました。今回はフォトグラファーで電動車いすユーザーである近藤浩紀さんにおすすめいただいた、東急電鉄・二子玉川駅構内のトイレに行ってきた模様をお伝えします。
2020.02.06