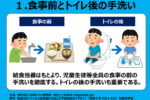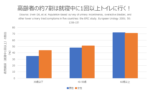日本トイレ研究所では「いい(11)トイレ(10)の日」にちなみ、毎年11月にフォーラムを開催し、すべての人が安心してトイレを利用でき、共に暮らせる社会について考えています。
「トイレに、愛を。フォーラム2018」レポート(後編)
前回に引き続き、2018年11月3日に実施した「トイレに、愛を。フォーラム2018」(協力・江戸川区)から、「これからのバリアフリートイレ」と題した意見交換の模様をお届けします。
意見交換のパネリストは、上原大祐さん(パラリンピック銀メダリスト)、立原直正さん(江戸川区土木部長)、奈良裕信さん(国土交通省総合政策局安心生活政策課長)、進行は加藤篤(NPO法人日本トイレ研究所)です。ここでは、これからのバリアフリートイレを考えるポイントとして、「設計」「マナー」「情報共有」に関する発言要旨を以下に示します。(役職等はすべて2018年11月時点)
バリアフリートイレの設計
はじめに「設計」についてお話しいただいたのは、国土交通省の奈良さんです。

政府では、東京オリンピック・パラリンピックを契機に「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を策定し、共生社会の実現に向けて取組を進めております。国土交通省では、高水準のバリアフリー化や、心のバリアフリーを推進する一環として、様々な障がいのある人が利用しやすいトイレ環境の整備を行っております。
近年、多機能トイレの整備が進んでいますが、国土交通省が実施したアンケートでは、車椅子使用者のうち約95%の方が多機能トイレを利用しようとして待たされた経験があり、うち約71%の方が障がい者に見えない人が多機能トイレから出てくることを経験したという結果が出ております。
こうした実情も踏まえ、国土交通省では、ハード・ソフトの両面から多機能トイレの利用集中の軽減に取り組んでおります。
ハード面として、平成29年3月に「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」、平成30年3月に「交通バリアフリー基準※1」及び「バリアフリー整備ガイドライン※2」の改正を行い、多機能トイレにまとめられた設備について車椅子使用者用、オストメイト用、乳幼児連れ用など可能な限り複数のトイレへの分散を図ることとしました。
ソフト面として、平成30年3月下旬から4月上旬に多機能トイレの利用マナー啓発のため、都道府県、公共交通事業者等の協力の下、ポスターの一斉掲示やチラシの配布によるキャンペーンを実施するとともに、街中でのトイレの位置や、トイレ入口の表示板などで機能付きトイレの配置を案内するなど、情報提供の充実を図っております。引き続きこれらの取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
※1)移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
※2)公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン
バリアフリートイレのマナー
続いてマナーについてお話しいただいたのは上原さんです。
食事マナーを例に、マナーは知ることから始まると語る上原さん。フランス料理は作法が厳しく決められていますが、作法を知らなければ実践することは不可能です。このように、知ることで行動や意識付けにつながることはたくさんあります。
現在の日本において、マイノリティに関する情報は、知る機会が限られています。バリアフリーに対する意識も、自ら得ようとしなくてはなかなか知る機会がありません。電車内の優先席については多くの方が知っていると思いますが、新幹線に車いす対応の座席があることをご存知でしょうか。お恥ずかしながら、私自身も上原さんのお話を伺うまでは全く知りませんでした。
車いす対応座席はシステム上、だれもが予約が出来るため、埋まってしまっている場合が少なくありません。その場合は、目的地に着くまで、車いすに乗ったまま利用できるトイレなどがある車両のデッキ部分にいることになります。多くの人が車いす対応座席の存在を知れば、知ったその時から車いす利用者への配慮の意識が芽生えます。すでに周知されている電車の優先席でさえ、座席の色やデザインを変えるといった工夫をしています。
上原さんが言うように、マナーは知ることから始まります。知るためには啓発や情報の共有が重要です。

バリアフリートイレの情報共有
最後は立原さんに情報共有についてお話いただきました。
上原さんのお話にもあったように、情報の共有はとても大切ですが、ただ情報を発信するだけでは啓発には繋がらないと立原さんは指摘します。大切なのは理由を添えて情報を伝えること。例えば、多機能トイレの利用方法について、健常者は利用してはいけないと禁止するだけでは、納得できず受け入れてもらえません。一時的に利用者が減少したとしても、本当の意味で理解がなされていなければ啓発は成功とは言えません。障がい者にとっては健常者用のトイレは使用しづらく、快適にトイレを利用するには多機能トイレが必要不可欠だと周知することが大切です。
そのためには積極的に情報共有の場を設けて繰り返し啓発を行うこと、同時に様々な意見に耳を傾ける姿勢が欠かせません。
“お気に入りトイレ”を募集しました!
日本トイレ研究所では以前から、トイレの困りごとに関する情報を、アンケート調査を通じて集計していました。多くの方にご協力をいただき、困りごとの情報を多く収集することができましたが、全てを一度に改善するのは難しい実情がありました。
そういった背景から、本フォーラムでは新たに「お気に入りトイレ」の情報を集める取り組みをスタートする宣言を行いました。皆さんにとって使いやすいトイレの情報を集め、どういったポイントが評価されているのかを抽出することで、トイレの改善に生かすことがこの取り組みの目的です。
本フォーラムの宣言をきっかけに、「お気に入りトイレ」の募集を2018年11月~2019年4月に行ったところ、さまざまな方にご協力をいただき、226件の回答が集まりました。
「お気に入りトイレ」のアンケート結果については、こちら(PDF)で紹介しています。
また、現地調査の模様を、トイレマガジンの記事で紹介しています。
今後も障がいを持つ方や、介助者の方、LGBTの方、高齢者や小さなお子様連れの方々など、さまざまな方からご意見ををもとに、課題の発見や解決につなげていきたいと思います。
今の気持ちを表してみよう!
PICK UP合わせて読みたい記事
-
 そのほか
そのほかトイレと排泄事情~妊娠出産を経験して~
妊娠出産による体の変化とトイレ・排泄事情について。妊娠中、出産後の女性にとって、どんなトイレ環境がいいのか、体験談をご紹介します。
2020.09.24
-
 おすすめトイレ
おすすめトイレ女子トイレの問題!生理への対処(MHM)を意識して
女性特有のトイレ・ニーズとして生理への対処があります。発展途上国では特に大きな問題ですが、日本の女子トイレ・ニーズにも共通する点があります。
2021.02.04
-
 おすすめトイレ
おすすめトイレNO MORE、トイレ難民!さて、トイレ難民ってだれのことでしょうか?
幼児期から高齢者までオムツ替え等の目的で利用できる『ユニバーサルシート』は、多目的トイレに設置されているベッドです。 しかし認知度はまだまだ低く、設置も進んでいないのが現状です。
2021.08.05
-
 おすすめトイレ
おすすめトイレ公共トイレってなんだ?
ダイバーシティから考える日本のトイレ問題について、地方公務員でNPO法人・両育わーるど理事長の星野勝太さんの連載を3回にわたりお届けします。第2回は「公共トイレってなんだ?」です。
2020.05.28
-
 おすすめトイレ
おすすめトイレ排泄に関わる障害を持つ「オストメイト」と日本初のスマートフォンアプリ
病気や障害はさまざまな種類があり、外見から分かりやすいものもあれば、一目見ただけでは健康な状態と変わりないといったものもあります。人工肛門、人工膀胱もその中の1つと言え、この人工肛門や人工膀胱を造設した方々をオストメイト […]
2022.02.10